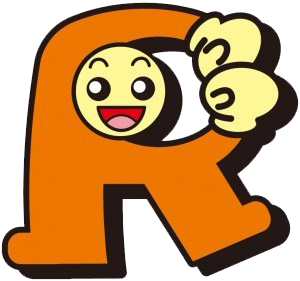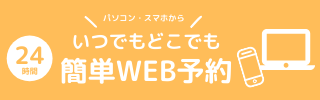カイロプラクターのための栄養学 第14期 第1回オンラインセミナー受講記
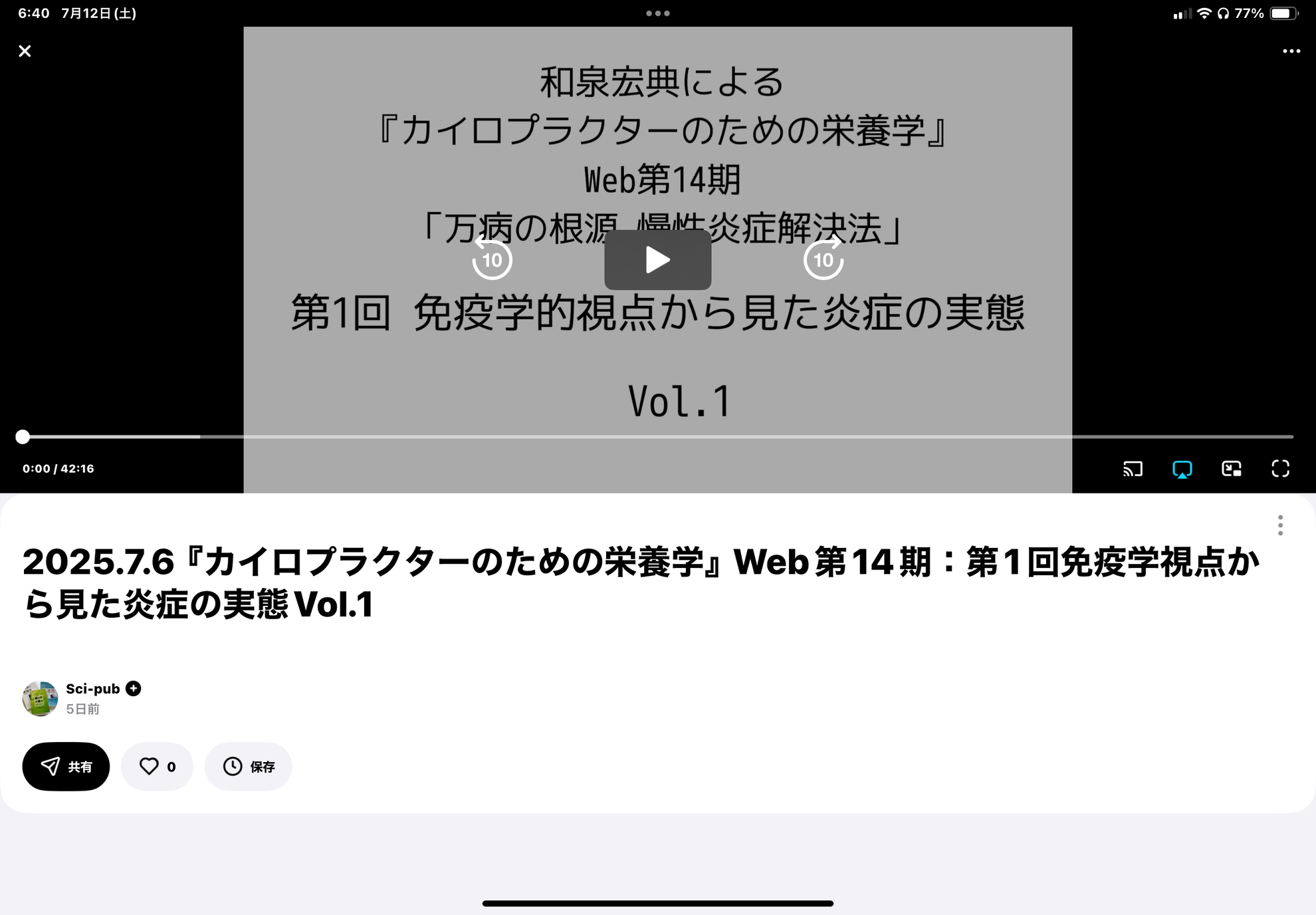
なぜこのセミナーに参加したのか
痛みがなかなか引かない。
通い続けているのに、すぐにぶり返してしまう。
本人も施術者も「何かが引っかかっている」と感じながら、その“何か”の正体が掴めずにいた。
この違和感の正体が「炎症」なのではないか──
そう感じたのは、ある患者のテニス肘に向き合っていたときだった。
マッサージや電気治療を受け、痛み止めを飲んでも変わらず、運動をやめる気配もない。
本人は「そこまでひどくない」と言うが、改善の兆しは見えない。
この停滞感の裏側にある「からだの仕組み」を理解し直すため、和泉先生のセミナーに参加した。
印象に残った言葉や場面(気づき)
「私たちが扱っているのは“痛み”ではなく、“炎症”である」
この一言が、強く胸に残った。
施術で反応が出ないとき、“筋肉が硬い”“神経が興奮している”といった表面的な捉え方にとどまっていた自分に気づかされた。
実際には、そこに“静かに燃えている火”=炎症があり、
私たちはその火に気づかず、水をかけるどころか、風を送ってしまっていることすらある。
まさにテニス肘のような症状に、身に覚えがありすぎた。
その内容が何を意味していたのか(学びの本質)
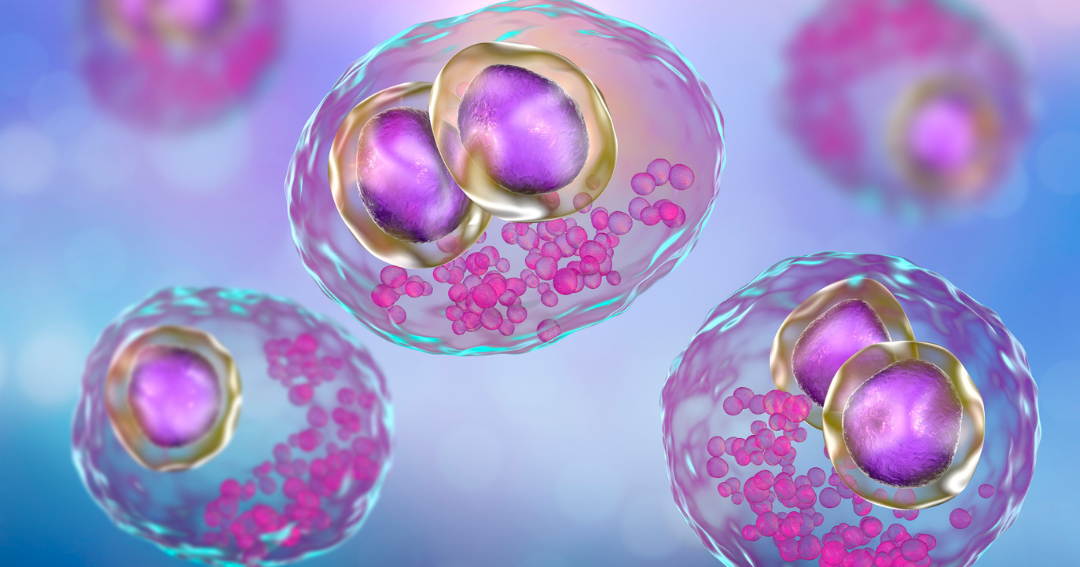
炎症とは、怪我や感染などへの防御反応。
本来は“治すため”に起きているものだが、うまく終わらせることができなければ「治らない痛み」へと姿を変えてしまう。
からだは、炎症を終わらせるために
-
好中球(こうちゅうきゅう)=最初の応援部隊
-
単球(たんきゅう)→マクロファージ=掃除係
-
さらにその終息の合図としてリゾルビンやプロテクチンが必要
といった、精密な段取りを用意している。
しかし、炎症が長引きすぎると
新しい血管を作りすぎたり(=血管新生)、
傷跡が硬く残ったり(=繊維化)して、回復そのものが阻まれてしまう。
こうした“回復できない構造”が、痛みを長引かせていたと気づいた。
現場にどう活かすか

テニス肘を例にすれば、
痛みがあるのに運動を続ける → 酸素不足になる → 血管が増える → 応援部隊が止まらない → 炎症が収まらない
というループが、本人の自覚なく進んでいた。
こうしたケースに対しては、
-
なぜ今「休む」ことが大切なのか
-
鎮痛剤が“火を止めるはずの合図”を消してしまうこと
-
青魚に含まれるDHAが“炎症を終わらせる材料”になること
-
治癒に必要なのは「動かす」よりも「整える」ことだということ
を、言葉を選びながら伝えるようになった。
ときに施術よりも、伝え方の方が回復を左右する。
それを、この講義を通して実感している。
からだが出している“火のサイン”に、耳を澄ませてみる。
その痛みは、何を知らせているのだろうか。
治ろうとして起きている反応ならば、
必要なのは“抑える”ことではなく、“終わらせる”ことなのかもしれない。