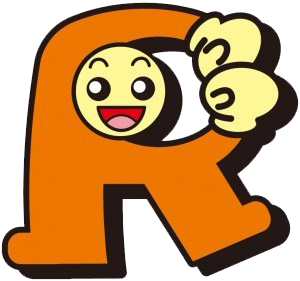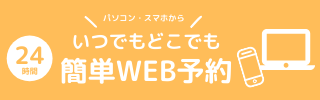——「痛みを感じにくくする仕組み」が、実は脳にあった
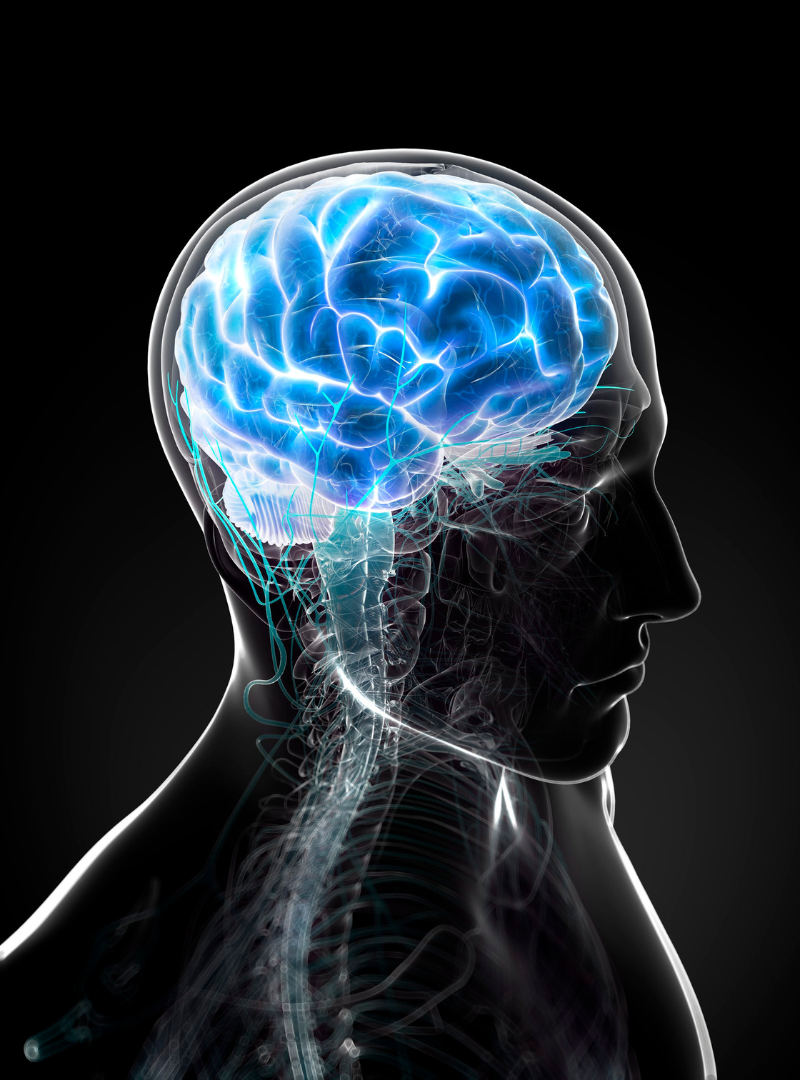
「痛みを抑えるスイッチ」が脳にある?
「痛みを感じるのは脳だ」という話はよく耳にしますが、実はその逆もあるんです。
✅ 脳は“痛みを感じにくくする”働きも持っている
この仕組みは「下降性疼痛抑制(かこうせいとうつうよくせい)」と呼ばれ、
痛みの信号が背骨(脊髄)から脳へ伝わる途中で、ブレーキをかけて抑える働きのことを指します。
どうやって痛みを抑えているの?

このブレーキ役を担っているのが、脳幹にある「PAG(中脳水道周囲灰白質)」という部位。
ここから:
-
正中縫線核(セロトニンを分泌)
-
青斑核(ノルアドレナリンを分泌)
といった神経ルートに命令が出て、
✅ 脊髄に向かって「痛みを止めろ!」という信号が下りていく
= これが「下降性」の由来です。
この働きがうまくいかなくなると…
本来あるはずの「痛みを抑えるブレーキ」が効かなくなると、
わずかな刺激にも過剰に反応してしまう「慢性痛」「広がる痛み」が起こりやすくなります。
☑️ レントゲンでは異常なし
☑️ でも痛みが取れない
☑️ ストレスで痛みが増す
こういったケースでは、構造の問題ではなく、脳の抑制機能の低下が関係している可能性があります。
アールカイロのアプローチ
私たちは、単に筋肉や骨格を見るだけでなく、脳と神経の「感じ方」や「スイッチの反応」を見ています。
✔︎ 施術のポイント:
-
やさしい感覚刺激(皮膚・関節・呼吸・目など)で、脳を安心させる
-
刺激の“量”ではなく“質と順番”を重視
-
痛みの「伝達経路」ではなく「抑制経路」に働きかける施術設計
なぜ“強く押す施術”が逆効果のこともあるのか?

下降性疼痛抑制が働いていないときに、強い刺激を入れると──
❌ 痛みの回路がさらに過敏になり、「触れられること=痛み」と脳が記憶してしまうことがあります。
だからこそ、“やさしくて深く届く刺激”が必要なのです。
痛みの原因は「感じ方」のスイッチかもしれない
✔︎ 脳には「痛みを感じにくくする」仕組みがある
✔︎ それがうまく働かないと、小さな刺激でも痛くなる
✔︎ アールカイロでは「痛みのブレーキを戻す」アプローチで対応します
「レントゲンでは異常なし」と言われたけど痛みが続いている方
「慢性痛にずっと悩まされている」方
まずは神経の“感じ方”を見直すことから始めてみませんか?