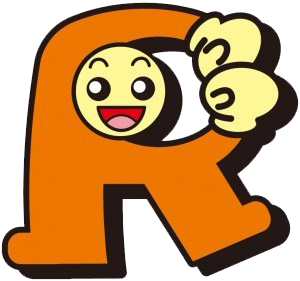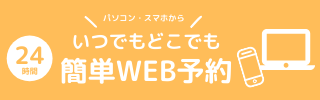——動きと神経の関係をやさしく解説します
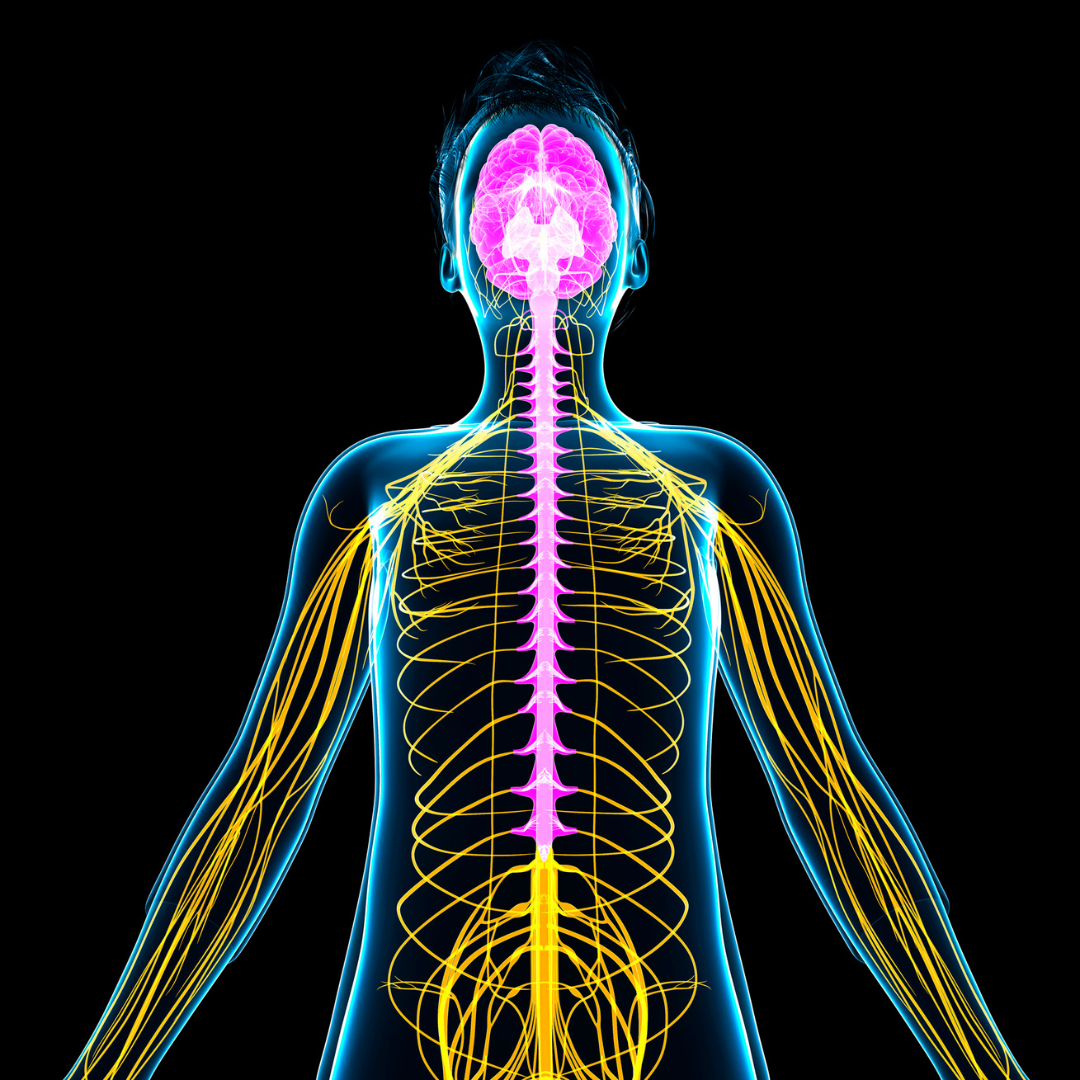
「力が入りにくい」「動きがギクシャクする」…
それ、筋肉の問題だけじゃないかもしれません。
アールカイロでは、しびれや痛みだけでなく、
「なんとなく動きづらい」「姿勢が安定しない」といった悩みについても、
神経の“伝わり方”と“感じ方のズレ”に注目して見ています。
今回は、そんな“動きと神経”のつながりについて、
医療現場でも使われている考え方をもとに、できるだけわかりやすくまとめてみました。
動きのしくみは「感覚」から始まっている
「手を動かす」「足を出す」など、私たちが普段している“動き”には、
実は先に「感覚」が必要なんです。
-
今どこに体があるか?
-
どのくらい重いのか?
-
触れているものは柔らかい?硬い?
これらの感覚情報をもとに、脳や神経が“どう動かすか”を判断し、筋肉に指令を出す。
▶︎ 感覚と運動はセットでループしていて、どちらかが崩れるとうまく動けなくなります。
スムーズな動きには「2つの情報更新」が必要
動きを上手にするには、次の2つの情報を常に脳で“更新”し続けている必要があります。
| 種類 | 内容と役割 |
|---|---|
| ① 脳の中のコピー情報(遠心性コピー) | 「自分は今こう動いたぞ」という内部記録。ズレを修正するために使う。 |
| ② 外からの感覚情報 | 実際に動いた結果どうだったか?というフィードバック情報。 |
▶︎ このふたつを常にすり合わせているからこそ、細かい動きが“自然に”できるんです。
「動き」にもいろいろな種類があります
| 動きの種類 | 説明例 |
|---|---|
| 運動 | ただの“物理的な動き” (例:ボールが転がる) |
| 行動・行為 | 意図や目的がある動き(例:ボールを投げる) |
| 随意運動 | 自分の意志で動かす動き(例:手を上げる) |
| 付随運動 | 意図せず起きる動き(例:震え、勝手に動く、力みなど) |
▶︎ 「本人の意思」と「神経の誤作動」は切り分けて考える必要があります。
動きがうまくいかないときに出る“サイン”
| 部位名 | 主な役割 |
|---|---|
| 第一次運動野 | 実際に筋肉を動かす命令を出す |
| 補足運動野 | 両手の動き・連続動作など、複雑な動きを組み立てる |
| 運動前野 | 動作の準備、目的に応じた力加減などの調整 |
| 運動眼野 | 目の動きをスタートさせる(視線を送る・追うなど) |
▶︎ 一か所だけでなく、「チーム」で動きをコントロールしているのが脳の仕組みです。
動きがうまくいかないときに出る“サイン”
たとえば、神経の命令を伝える「錐体路(すいたいろ)」という通り道に問題が起きると…
| サイン例 | どうなるか |
|---|---|
| 弛緩性麻痺(初期) | 力が入らず、腕や足がダラッとする状態に |
| 痙性麻痺(時間が経つと) | 力が入りすぎて、手足がこわばったまま曲がる |
| 深部腱反射の亢進 | ハンマーで叩いたときの反射が異常に強く出る |
| 病的反射の出現 | 通常では出ない反応(例:足の裏をこすると指が開く)などが現れる |
| 表在反射の消失 | 皮膚をさすっても、本来出るはずの反応が出ない |
▶︎「異常な動き方」が出る背景には、神経系の混乱が隠れていることがあるのです。
原因は“脳の病気”だけとは限りません
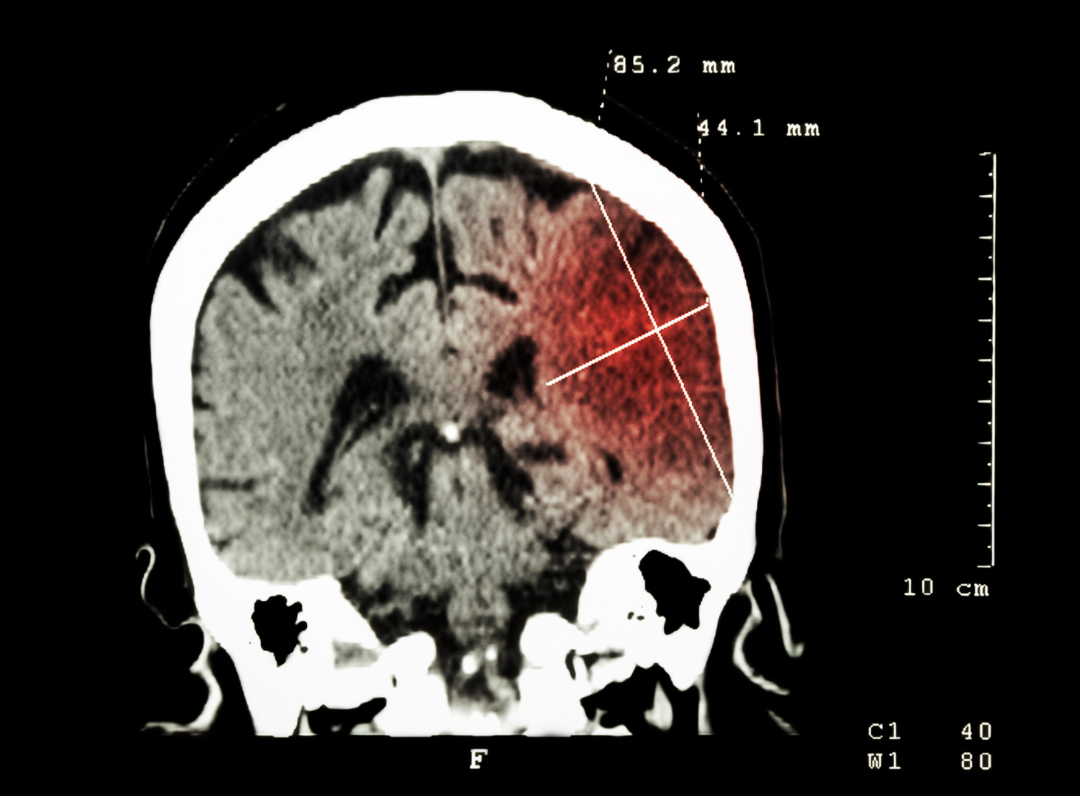
-
脳梗塞や大けがのような明らかなダメージでなくても、
-
酸素・栄養(特に糖)・感覚刺激が不足するだけでも、神経の働きは落ちてきます。
▶︎ 「なんとなく力が入りづらい」「動きがぎこちない」というのも、神経の状態低下のサインかもしれません。
アールカイロが動きを見るときに大切にしていること
当院では、「どこが悪いか」よりも、
「どう動いているか」「どこにズレがあるか」「反応に違和感があるか」という視点で観察しています。
-
神経の状態は*固定”されたものではなく、日々変化します
-
検査や動きの観察で、その日の状態を見極めることがとても大切
-
小さなサインに気づき、刺激・呼吸・姿勢などから整える順番を組み立てる
▶︎ 大切なのは「動き」を追うことではなく、“動き方”に隠れた神経の状態を見抜くことです。
こんな方は一度ご相談ください
-
最近なんとなく力が入りにくい
-
歩くときにバランスが崩れやすい
-
検査では異常なし。でも動きに違和感がある
-
姿勢や筋肉の問題だけではない気がする
▶︎ 初回カウンセリングでは、神経と動きの関係を検査と動作評価で丁寧に確認します。
▶︎ 不安な方は無料LINE相談はこちら