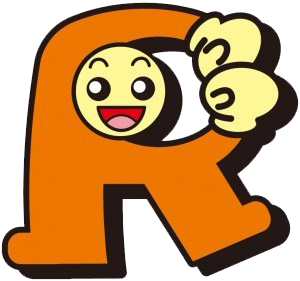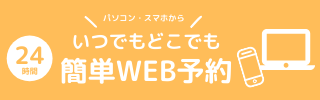──末梢と中枢、2つの痛みの違いを理解する

「痛み止めを飲んでも効かない」
「ブロック注射を打っても、その場だけで戻ってしまう」
こうした悩みを抱えたまま、整形外科や整体を何院も回り、それでも改善せず、ようやく当院に辿り着く方は少なくない。
結論から述べると、“効かない痛み止め”を責める必要はまったくない。
なぜなら痛みには“末梢”と“中枢”の2つのレベルがあり、鎮痛薬はそのうち片方にしか作用しないからである。
以下では、神経学の視点を踏まえ、鎮痛薬と慢性痛の関係を「どう理解すべきか」「どう向き合うべきか」を整理する。
■1.痛み止めは“体の痛みを感じる場所”には効くが、“痛みの感じ方を調整する脳のほう”には効かない。

鎮痛薬(ロキソニン・アセトアミノフェン・湿布・ブロック注射)は、基本的に末梢の侵害受容器の発火を抑える薬である。
炎症が起きている・組織が損傷している・受容器が刺激されて痛みが出ている──こうした“末梢主導型の痛み”には効果がある。
いわゆる捻挫・打撲・ぎっくり腰の初期などが典型例である。
しかし、これは痛みのごく一部であり、痛みの主要部分は脊髄-脳(中枢)で処理されている。
痛み止めが効かないケースは、この「中枢側」が原因になっている。
■2.慢性の痛みやしびれ、むずむず脚症候群は、体の問題というより“脳の感じ方が敏感になっていること”が原因で起こる。
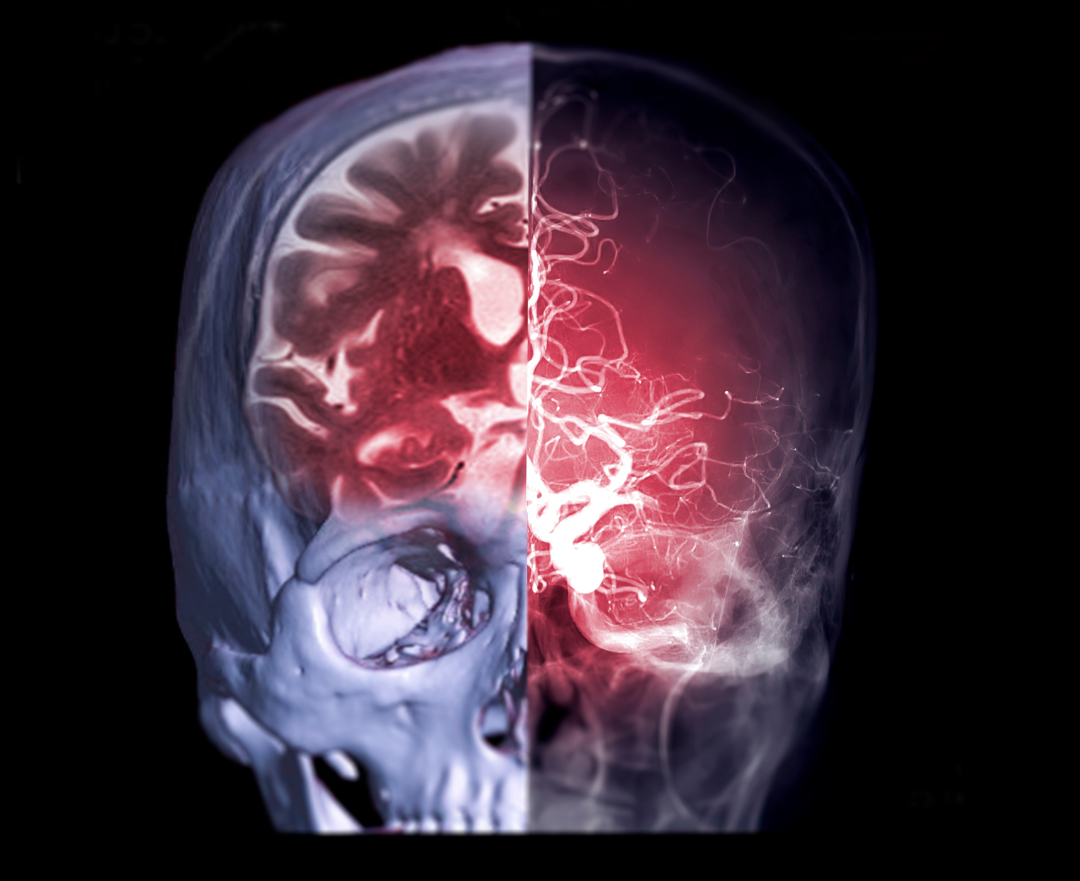
長く続く痛み、しびれ、むずむず脚症候群、不安を伴う痛みなどは、
実は “体のセンサー” ではなく 脳の処理のほうが敏感になってしまうこと が原因である。
脳のなかには、
・痛みを受け取る場所
・痛みを「大したことない」と処理する場所
・不安やストレスと痛みを結びつけてしまう場所
など、複数の部位が連携して働いている。
これらが疲れたり過敏になると、
本来痛くないはずの弱い刺激でも“痛い”と感じやすくなる。
つまり、
“ケガが治っていない”のではなく、
“痛みの処理をする側の過敏さ”が続いてしまっている状態である。
そして、
鎮痛薬は体のセンサー(末梢)には効くが、
脳の過敏さには届かないため効きにくくなる。
■3.ブロック注射は“その場の痛み”には効くが、“痛みの感じ方が過敏になっている状態”までは変えられない。

一時的にラクになるけれど、またすぐ元に戻ってしまう──
これはブロック注射でよく起こる現象である。
理由はとても単純である。
ブロック注射は「痛みを感じる場所(現場)」だけを一時的に落ち着かせる方法だからだ。
ところが、長く続く痛みの多くは、
実は 脳のほうが“痛みに敏感な状態”になっている ことで強まっている。
例えるなら、
・火災報知器(脳)が過敏になっていて
・弱い煙(体の刺激)でもすぐ鳴ってしまう
そんな状態である。
ブロック注射は「煙を一瞬だけ減らす」ことはできるが、
火災報知器そのものの敏感さは変えられない。
だから、
「効いたけれど、またすぐ戻る」
という流れになりやすい。
■4.“痛み止めが効かない=重症”ではまったくない
誤解しやすい点だが、「薬が効かない = 病状が悪化している」わけではない。
み止めが効かないのは、痛みの“センサー”ではなく、痛みを処理する“脳のほう”が敏感になっているためである。
これはむしろ改善のヒントであり、
「薬で抑える」のではなく「神経を落ち着かせるアプローチ」に切り替える良いタイミングといえる。
■5.むずむず脚症候群は、痛み止めが効かない典型的なケース

むずむず脚症候群(RLS)は、
足が落ち着かない・じっとしていられない・夜になると特にムズムズする
といった症状が出る状態である。
この症状は、足に炎症があるわけでも、筋肉が傷んでいるわけでもない。
原因は “脳の中のリズムが乱れてしまうこと” にある。
つまり、
足よりも「感じ方のほう」が疲れて乱れている状態 である。
そのため、
いくら痛み止めを飲んでも、足に湿布を貼っても、
症状がほとんど変わらないのである。
ではどうするか。
-
深い呼吸
-
軽く動かすこと
-
姿勢を整えること
-
足や体にやさしい刺激を入れること
こうした 「脳のリズムを整える方法」 が大切である。
足そのものを治すというより、
足の“感じ方”を落ち着かせることが必要 というわけである。
■6.効かない薬を続けるほど、脳は鈍くなる

慢性痛における中枢感作は“痛みの学習”である。
痛み止めを漫然と続けても、痛みの元となる回路をリセットすることはできない。
むしろ、
・痛みを避ける
・体を動かさない
・呼吸が浅くなる
こうした習慣が続くほど、脳は“痛い状態を学習し続ける”ことになる。
改善が遅れる理由はここにある。
■7.慢性痛には“中枢を落ち着かせる方法”が必要

痛み止めが効かない痛みは、体ではなく“痛みの感じ方そのもの”が敏感になっていることが原因で起こる。
このタイプの痛みには、
薬では届かない“感じ方のリセット”が必要になる。
そのために役立つのは、次のようなシンプルな方法である。
-
深い呼吸
→ 体が落ち着き、痛みに敏感になっている状態をゆるめる。 -
姿勢や胸の動きを整える
→ 呼吸が入りやすくなり、体がリラックスしやすくなる。 -
軽く体を動かす
→ “痛みを和らげるスイッチ”が自然に入りやすくなる。 -
皮膚や体へのやさしい刺激
→ 過敏になっていた「痛いと思い込みやすい回路」が落ち着く。 -
あたためる/冷やすなどの適度な温度刺激
→ 痛みを感じるセンサーが正常に戻りやすくなる。
これらはすべて、
身体が本来持っている“痛みを落ち着かせる力”を引き出す方法 である。
薬で痛みをごまかすのではなく、
“痛みの回路そのもの”を整えていくアプローチといえる。
痛み止めが効かないことを心配する必要はない。
むしろ、「効かない理由」がわかれば、これから何をすればいいかがはっきりしてくる。
✔ 痛み止め・湿布・注射が効くのは、“体に起きている痛み”
(炎症やケガなど、わかりやすい原因がある痛み)
✔ 慢性的な痛み・しびれ・むずむず感は、“脳の感じ方が敏感になっている痛み”
(体よりも“感じ方のスイッチ”が強く入っている状態)
✔ このタイプの痛みは、薬ではなく“感じ方を落ち着かせる方法”が必要
✔ 深い呼吸・姿勢を整える・軽く動く・皮膚をやさしく刺激する──これらが有効
(身体が本来持っている「痛みを落ち着かせる力」を呼び起こす方法)
痛みを無理に抑え込むのではなく、身体のしくみをもう一度正常に戻していくこと。
それが、慢性的な痛みを根本から改善するための鍵である。