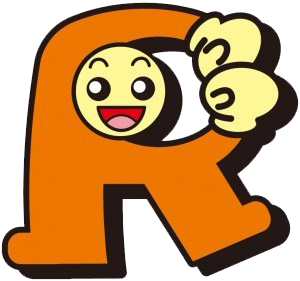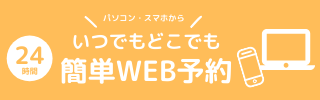── 自分で痛みを調整できる頭の動きとは?
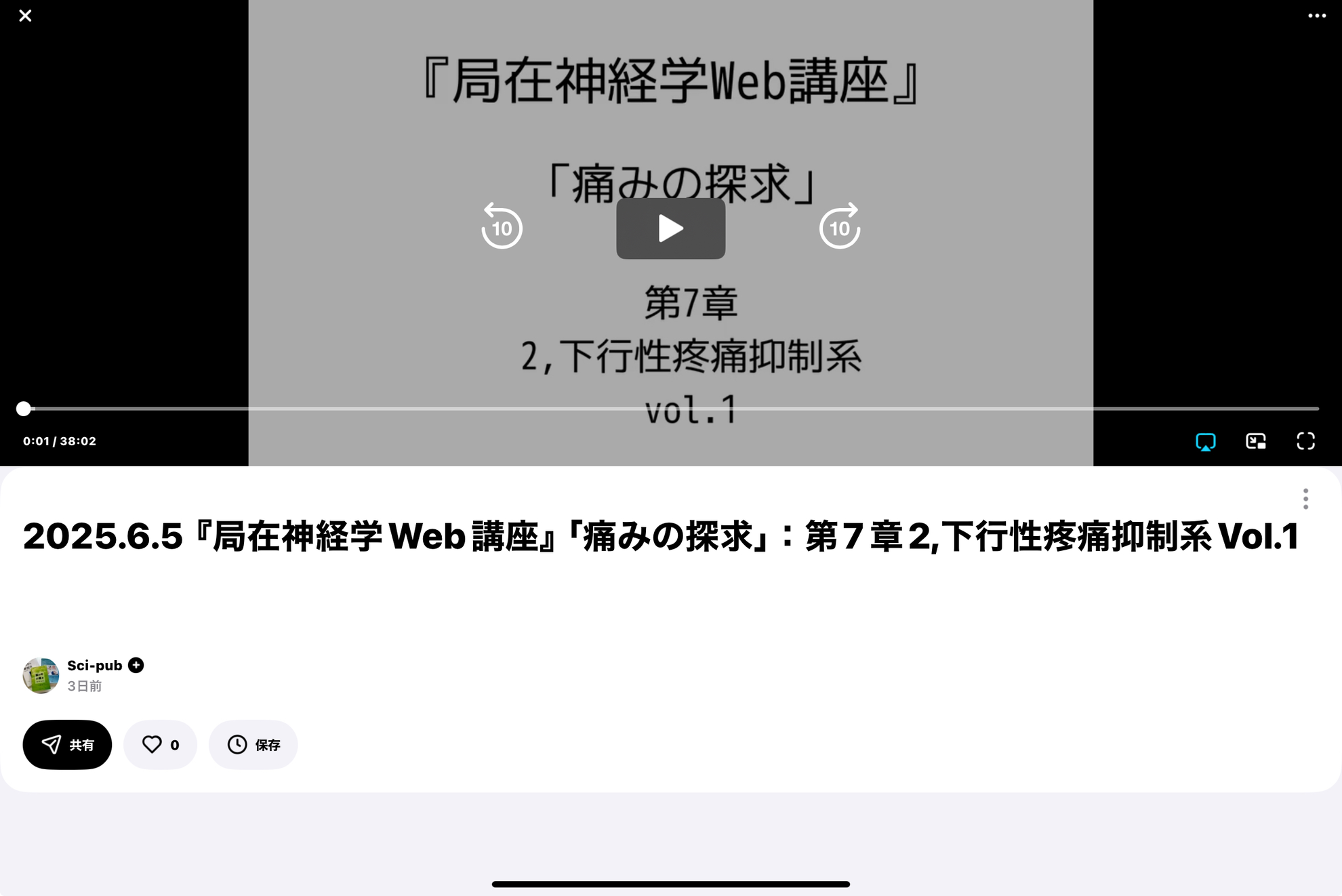
◆ はじめに:「痛み」は、ただ抑え込むものではない
痛みがあると、「悪いことが起きている」と思うのが普通です。
でも、痛みは体からの“サイン”であり、
自分の身体が「いま、気づいてほしい」と送っているメッセージでもあります。
そのメッセージをただ“怖いもの”として捉えてしまうと、身体は緊張し、脳は混乱し、
結果として「痛みが高まって治らない」という渦に巻き込まれていきます。
◆ 「痛みを自分で抑える仕組み」が、頭の中にはある
先日受講した「痛みの探究 第7章」では、
痛みを感じる“その後”に、脳がどんなフィルターをかけているか?という話がありました。
脳の中にあるPAG(中脳水道周辺灰白質)という場所には、
「これは危険な痛みなのかどうか?」を判断し、
必要以上の痛みをシャットアウトする“抑制装置”が備わっています。
ところがこのPAGは、「怖い」「不安」「信じてもらえない」といった感情や、
感覚がズレていたり、日常の習慣が乱れていたりするだけで、すぐに働かなくなってしまいます。
◆ 「原因不明」と言われた人ほど、この仕組みが止まっている
-
検査で異常なしと言われた
-
画像に何も写らない
-
痛み止めが効かない
──そんな方ほど、
このPAGを含む「中枢性の抑制系(=痛みをコントロールするシステム)」がうまく働いていない可能性が高いのです。
◆ 鍵は、「豊かな頭の動き」にある
PAGを含む脳の痛み調整システムが働くために必要なのは、
じつは「動かせる身体」ではなく、“動いている頭”です。
-
感覚がズレていないか?
-
姿勢や呼吸、味覚など、“身体を味わう感性”が使われているか?
-
「それでいい」と感じられる感性があるか?
これらを感じ取る「頭のフィルター」が回復すれば、
身体は“痛みを必要以上に出さないモード”に戻っていきます。
◆ 施術は「姿勢や感覚の再構築」に向かう
これから当院は、
この“フィルター”を整え直すためのサポートとして、
-
姿勢の再設計
-
感覚の調律
-
頭と身体の連動回復
を意識したアプローチに、さらに注力していきます。
◆ 最後に:「知識」とは、“見逃さない”ための力
痛みを「その場所」で判断するのではなく、
「なぜ出ているのか」「どう出しているのか」を見抜く力。
その力を持つために、私たちは知識を追い続けています。
「やっと、わかってくれる人に出会えた」
そう思ってもらえるような施術家であるために、
私はこれからも“痛みを理解する知識”を学び続けます。