流体筋膜動可法とは
「血流はいいのに、なぜ不調が残るのか?」
最近は、
-
血流をよくするための施術
-
自律神経を整える呼吸法
-
鉄・ビタミン・プロテインを補う栄養療法
など、“巡らせるためのケア”が広がりつつあります。
しかし、血流や栄養が届いているはずなのに、症状が改善しない方が多くいます。
その理由は、“通り道”がつぶれているからかもしれません。
間質液──筋膜を巡る「もうひとつの流れ」
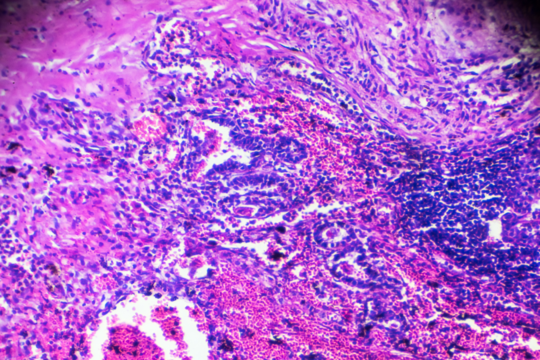
血管やリンパとは別に、筋膜の中を通っている「間質液(かんしつえき)」という水があります。
-
酸素や栄養を細胞に届ける
-
老廃物や炎症物質を排出する
-
神経周囲の環境を安定化させる
この間質液の通り道が筋膜の網目構造であり、そこがつぶれると水が止まり、神経過敏・炎症の長期化・回復力の低下につながります。
筋膜とは“動ける網目のネット”
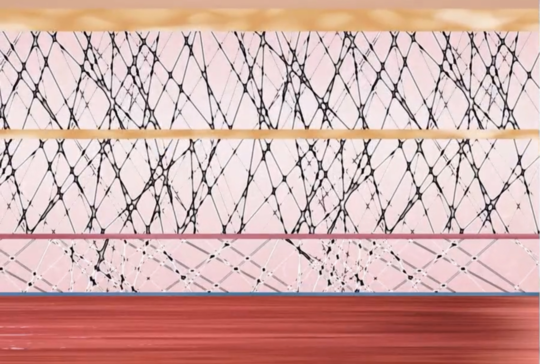
筋膜とは、皮膚〜筋肉の間に存在する、立体的な“結合組織の網”です。
筋肉を包む膜というよりも、動けるネット状の支持組織と考えるとわかりやすいでしょう。
その中を間質液が流れることで、体内の「細胞環境」が保たれています。
ところが──
-
姿勢の崩れ
-
筋膜のねじれ・癒着
-
使いすぎ/使わなさすぎ
などで網目がつぶれると、水は流れを失い、痛みやしびれが慢性化しやすくなります。
流体筋膜動可法とは?
流体筋膜動可法は、
「構造を整えることで、水(間質液)を巡らせる」
という新しいアプローチです。
-
マッサージや矯正のように“形を整える”のではなく、
-
血流促進や温熱のように“流れを強制する”のでもなく、
本来あるべき構造と圧力のバランスを整えることで、
体が自ら水を巡らせる力を取り戻すのがこの施術法です。
「定にして動も可」──それが構造の理想
この施術の根本にあるのが、キネシオ創始者・加瀬建造氏の考えた治療理念:
「定にして動も可」
──構造が安定(定)していながら、必要な可動性(動)をもっている状態
流体筋膜動可法では、まず身体の構造的安定(定)をつくり、
その上で間質液・呼吸・筋肉・神経が自然に動ける(動も可)状態に戻していきます。
体液を動かす「4つのハイドロギア」
水を巡らせるためには、「ポンプ」が必要です。
それが、次の4つの流動因子=ハイドロギアです。
| ハイドロギア | 機能・役割 |
|---|---|
| 重力 | 姿勢・内圧・下方への流れを生む |
| 呼吸(横隔膜) | 胸腔と腹腔をまたぐポンプとしての役割 |
| 心臓 | 血液と間質液の拍動的循環 |
| 筋肉 | 動き・テンション・滑走性による循環補助 |
これらが連動しているとき、身体は自動的に“流れる”モードに入ります。
空・動・冷──流れるための3条件
ハイドロギアがうまく機能すると、
キネシオテーピング理論でいう「空・動・冷」が自然に整っていきます。
| コンセプト | 意味 |
|---|---|
| 空(くう) | 間質液が流れる隙間(スペース) |
| 動(どう) | 組織が動くことで水も動く |
| 冷(れい) | 熱がこもらず、粘性が増えない状態 |
※「冷」は冷却ではなく、“熱がこもらず巡る”という意味です。
筋肉が緩まないのは「酸素と栄養」が足りないから
多くの方が「筋肉が硬い=緩めればいい」と思いがちですが、
筋肉を緩めるにはATPというエネルギーが必要です。
ATPは、酸素+栄養からミトコンドリアで作られます。
つまり、呼吸が浅い/血流が悪い/栄養が届かないと──
-
筋肉は緩もうとしても緩めない
-
慢性的に収縮したまま
-
神経を締めつけ、過敏化を招く
という悪循環に。
流体筋膜動可法では、
呼吸・姿勢・筋膜滑走性・間質液循環を整え、酸素と栄養が届く構造をつくることで、
筋肉が自然と緩む状態を目指します。
身体は「流すために歪む」ことがある
ゆがみ=悪、と考えられがちですが、
実は身体が間質液を流すために、あえて歪むことがあるのです。
-
苦しくなった場所から逃げるように歪む
-
水を送りたい部位のために、他の部位を犠牲にする
つまり、ゆがみは結果であり、原因ではない。
構造と流れを整えれば、身体は自然と本来の形に戻ろうとします。
検査では「異常なし」でも起こる不調に
レントゲンやMRIでは異常が見つからないのに、
-
しびれ・神経痛が消えない
-
慢性疲労・頭痛・息苦しさが続く
-
自律神経が乱れている感覚がある
このような**“機能性障害”**は、
構造と循環(間質液)を整えるアプローチによって改善の糸口が見えることが多々あります。
このような方におすすめです
-
「神経痛・しびれ」の根本的アプローチを探している方
-
姿勢の崩れや左右差に悩んでいる方
-
呼吸が浅い/疲れやすい/緊張しやすい方
-
病院では「異常なし」と言われたがつらさが続いている方
-
自分の回復力を高めたいと感じている方
-
流す前に、流れる構造が必要
-
緩める前に、酸素と栄養が届く仕組みが必要
-
整える前に、なぜ歪んでいるのかを見極める視点が必要
流体筋膜動可法は、
「定にして動も可」──構造を整え、動ける身体を取り戻すことで、
本来の流れと回復力を引き出していく施術法です。
- 手のしびれ・神経痛
- 足のしびれ・神経痛
- その他の症状