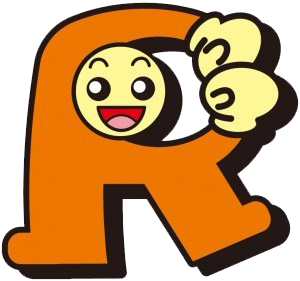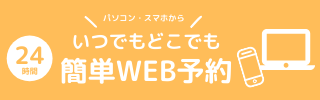第27回 キネシオテーピング協会 関東支部研修会 参加記
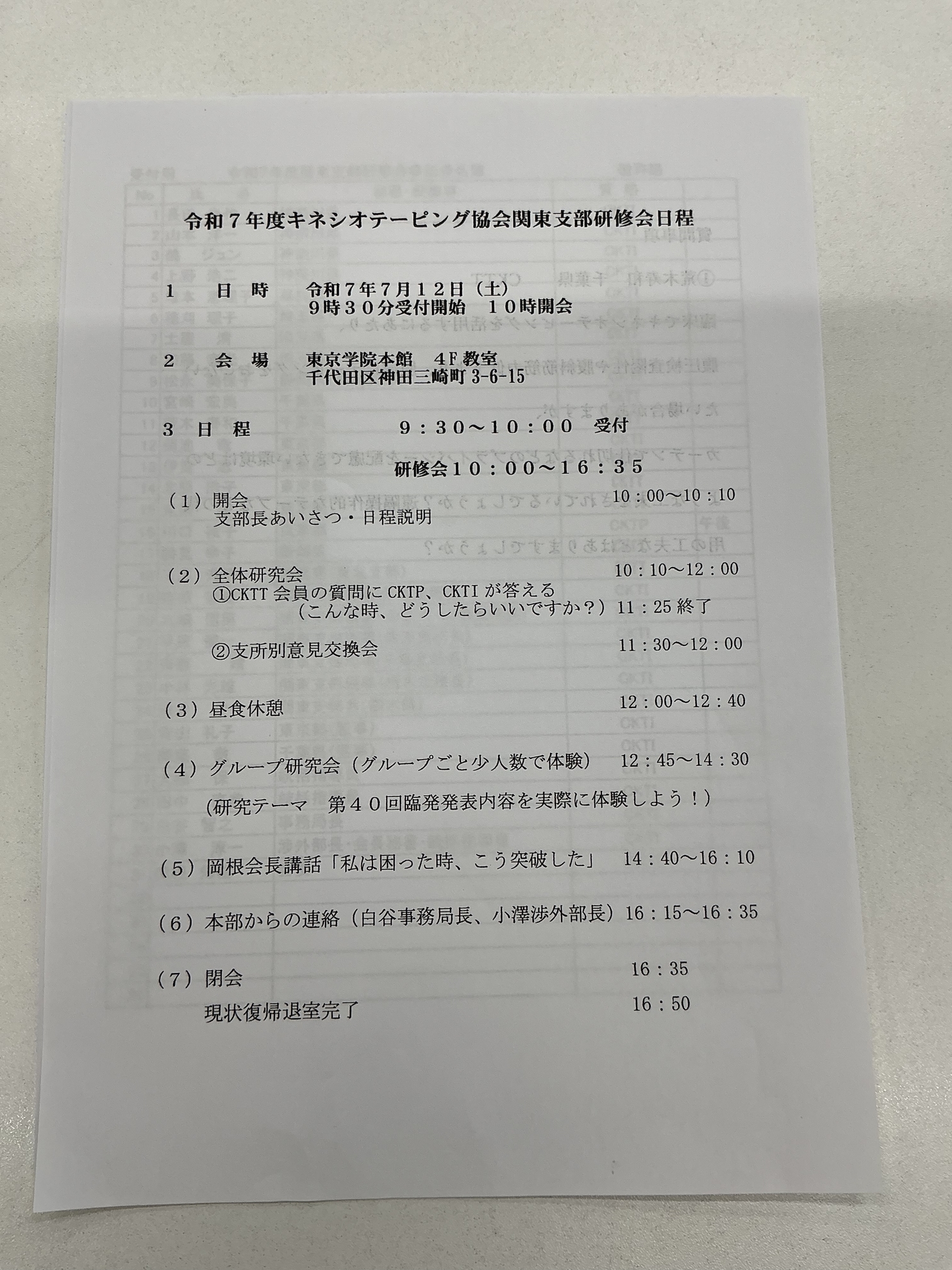
なぜこの研修会に参加したのか
この研修会に参加した目的は、
新しいテクニックを増やすことではなく、「問い続ける場」に身を置くこと。
ひとりで施術をしていると、つい自分の“わかる範囲”の中で判断しがちになります。
だからこそ、他の施術者の視点に触れ、違いを楽しみ、問いを深める機会を持ち続けたい。
また、現場で浮かぶ小さな疑問を誰かと共有しながら、
継続的に学び続けられる場所(=コミュニティ)に所属し続けること自体が、自分にとっての支えでもあります。
全体研究|“答えの違い”に意味がある
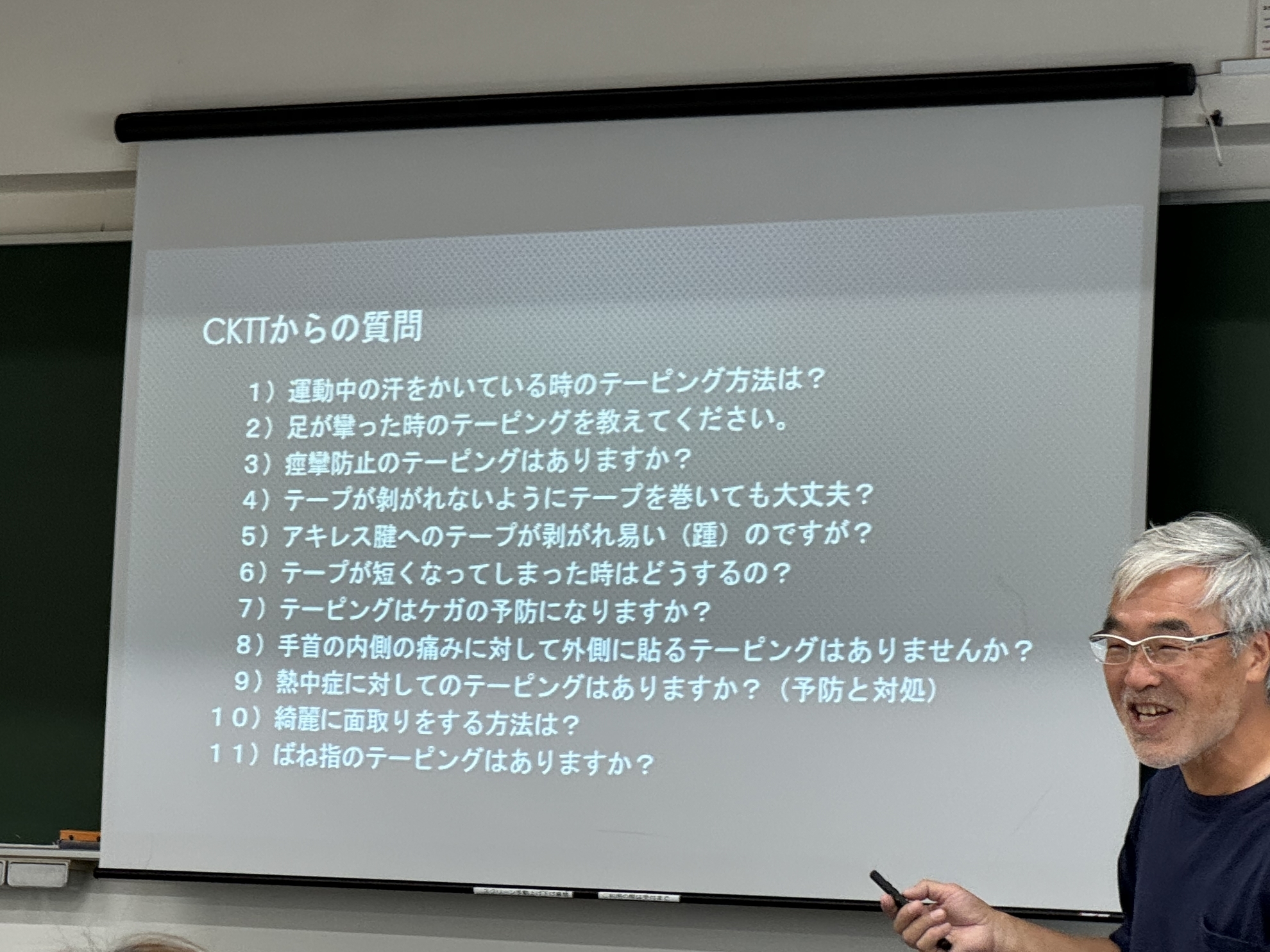
前半は、参加者から寄せられた質問をもとに行われた全体研究セッション。
CKTIやベテランの先生方が、各自の視点で実体験に基づいた回答をしていく中で、
「同じ症状でも、判断の起点が違えばアプローチも違う」ということをあらためて実感しました。
貼り方のテクニックではなく、
“どう見立てたか” “何を見てそう判断したか”という背景の思考が共有される時間。
答え合わせではなく、視点を増やす時間として、非常に濃い学びがありました。
グループ研究|実技と体感で“考える力”を育てる
後半は3班に分かれてのグループ研究・実技指導。
まず本部指導員・大橋先生による膝痛のデモンストレーションが行われ、
観察→判断→貼付→確認までの一連のプロセスが、治療さながらの空気感の中で展開されました。
「“見立てがすべて”」というメッセージが、深く響きました。
続いて各班では、
「立位体前屈」に対し、大腿の前面・後面に貼ったときの違いを体感するというお題に取り組みました。
CKTTの先生に貼ってもらいながら、
実際に前屈してみて体の変化を確認する中で、次のような気づきが生まれました:
-
貼る人によって、位置・テンション・角度が違う
-
知識や経験によって、狙う場所や変化の質が異なる
-
同じお題でも“結果が違う”という面白さがある
テーピングは、貼り方だけではなく、
「どこに・なぜ・どう貼るか」という“思考の深さ”が効果を左右する。
それを実感として理解できた貴重な時間でした。
岡根会長講演|技術の先にある“在り方”
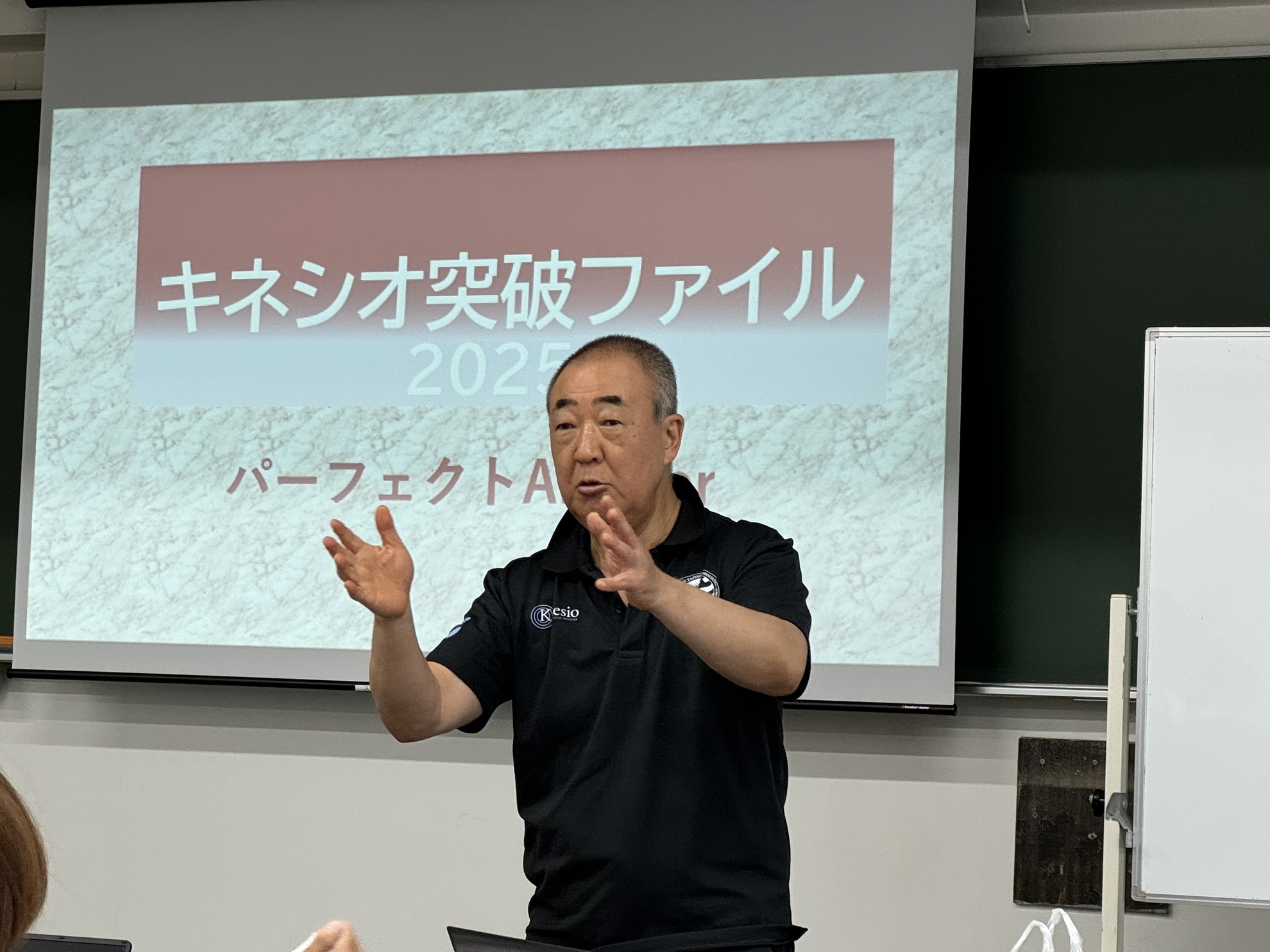
最後は、キネシオテーピング協会 会長・岡根知樹氏によるご講話。
AIから導き出したという「キネシオ突破ファイル」をもとに、
施術者として成長し続けるための視点が語られました。
印象的だったメッセージの一部:
-
「効かなかった時に、道具のせいにしていないか?」
-
「貼った後の“扱い方”ひとつで効果は変わる」
-
「疑念を持つのは悪いことじゃない。何を疑っているのか、言葉にしてみよう」
-
「自分の限界を知ることが、施術の質を上げる第一歩」
-
「“貼ること”は、治すことではなく、触れること・関係をつくること」
厳しさの中に温かさがあり、
技術だけでなく“施術者の在り方”そのものに光を当てる内容でした。
最後に、自分自身への問いとして
最近、こうした研修会や勉強会で、
「どう貼ってますか?」「先生ならどう見ますか?」と声をかけられることが増えてきました。
かつては自分が教えを求める側だったのに、
今は、教えることを求められる場面が増えている。
そのことに少しずつ、自覚と責任を持つようになってきました。
教えるということは、ただ知っていることを伝えるのではなく、
「自分の判断や感覚に、自分自身が答えられるか?」という問いに向き合うこと。
テーピングは、“貼ること”ではなく、“問いを込めること”。
だからこそ一本のテープに、「観察」「意図」「敬意」がこもっているかどうかがすべてです。
また明日から、
自分自身にも問いかけながら、一本一本のテープを丁寧に使っていきたいと思います。