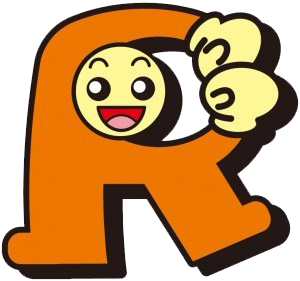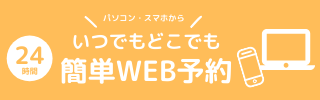しびれ・痛み・慢性症状の背後にある、見えないズレ

神経系の状態把握において、「検査こそがすべてである」──
そう強く感じる場面は、現場で日常的に起こっている。
痛み、しびれ、慢性疲労など、画像や整形外科的検査では“異常なし”とされるにもかかわらず、不調が続くケースは少なくない。
しかし、そのような症状の背景には、神経の“機能的なズレ”や“感覚統合の誤作動”が隠れていることが多い。
問題は、診断名が付くかどうかではなく、神経が「どう感じているか」「どう伝えているか」である。
こうした問題を適切に評価できるだけの検査力を身につけなければ、施術の精度も、説明の説得力も伴わない。だからこそ今回、神経学的検査の専門講座に参加し、現場で活かせる視点をあらためて学び直した。
「感じ方のズレ」は症状のズレとして現れる

神経には、「痛みを感じる」「触られたとわかる」「身体の位置を把握する」といった感覚系の働きがある。
これらはすべて、正確な入力があってこそ、適切な出力が生まれる。
入力にエラーがある状態では、出力(動作や痛みの感じ方)にも当然ズレが生じる。
たとえば、眼球運動に伴って顎が動いてしまう子どものケース、目を閉じた状態で腕を水平に挙げると大きくズレてしまう成人のケースなどがある。
中枢神経がうまく情報統合できていない状態では、こうした“ズレた反応”が随所に現れる。
しびれは「神経の誤作動」である

「しびれ=神経圧迫」と捉えがちだが、実際には酸素・栄養不足、または神経細胞の膜電位異常によって過敏化しているケースも多い。
チネル徴候(神経の走行上を軽く叩くと遠くの部位にしびれが出る反応)では、神経に明らかな損傷がなくても、細胞の電気的な閾値が不安定になっているだけで“ビリッ”と反応してしまうことがある。
また、来院者が訴えるしびれの範囲と、実際に痛覚が過敏になっている範囲が一致しないことも多い。
こうしたズレは、“本人の感覚地図”と“実際の神経反応地図”の乖離(かいり)であり、評価する側が冷静に見抜く力を持っている必要がある。
位置感覚(位置覚)と慢性痛の関係

目を閉じた状態で指差しをしてもらったり、腕を挙げてもらったりすると、「身体が今どこにあるか」という深部感覚(プロプリオセプション)のズレが可視化される。
この感覚が狂っていると、筋肉が過剰に働いたり、逆に出力が低下したりして、無意識のうちに身体に負担をかける動き方になる。結果として、慢性的な肩こりや腰痛、首の違和感につながることが多い。
実際、講座ではバランスパッドや鏡を用いたチェック法も紹介され、「視覚と感覚の統合」がうまくいかないと、出力(動作や姿勢)にも支障が出ることがあらためて確認された。
“神経を診る目”はまだ一般化していない

現在、神経の機能(感覚の伝達・統合・出力)を評価しながら施術に活かしている専門職はごく少数である。
日本国内でも、神経学を臨床に取り入れている民間施術者は限られており、むしろ誤解や抵抗を受けることすらある。
また、YouTubeなどで発信されている情報には、神経の構造や反射・調整メカニズムを正しく踏まえていない内容も多く、誤ったケアによって状態を悪化させてしまう可能性もある。
一方で、医療機関においても、命に関わる重大な神経疾患(例:脳梗塞など)でなければ、“機能のズレ”や“感覚の誤作動”はほとんど検査されない。画像に映らなければ「異常なし」とされ、訴えが放置されることも少なくない。
このような背景において、民間の施術者が神経系の状態を正確に把握し、身体の反応を冷静に観察しながら調整のサポートを行う意義は極めて大きいと感じている。
“異常がない”のではなく、“見ていないだけ”かもしれない
医療機関で「異常なし」と言われたとき、それは“機能のエラーが評価されていない”だけかもしれない。
✔ チネル徴候、痛覚の左右差、触覚・振動覚の違い
✔ 姿勢・視線・視野・赤目反射のズレ
✔ SPO2・心拍数の左右差、筋トーヌスの過不足
✔ 出力の非対称や位置覚のエラー
これらを多面的に観察し、神経の“感じ方・伝え方・動かし方”のズレを把握することで、改善への道筋は大きく変わる。
アールカイロでは、こうした神経学的視点をもとに、問診・検査・施術・セルフケアを統合し、
「どこに行っても良くならなかった」という方にこそ、“別の可能性”を提示できる存在でありたいと考えている。
まだ治らないとあきらめかけた方へ。
それは、「異常がない」のではなく、「診る視点が足りなかった」だけかもしれない。